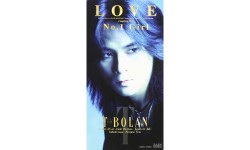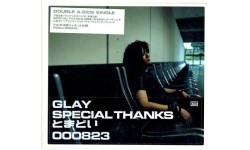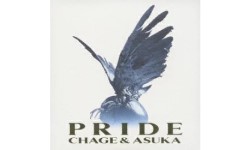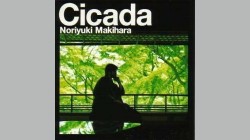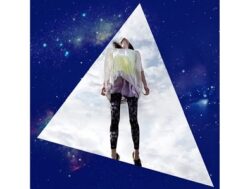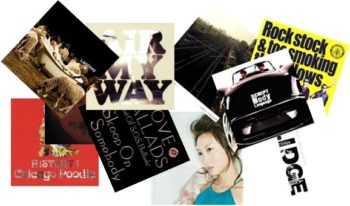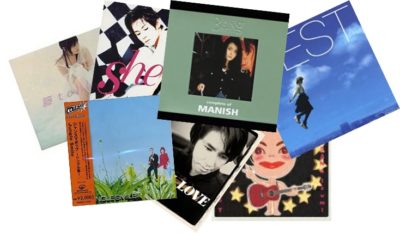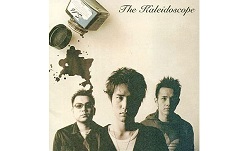【目次】
①90年代に入ったころのB'zは…
90年代に入ったころのB'zは、シンセポップからハードロックへと急激に進化していく過渡期。
その後のバンドサウンド全開なB'zもいいけど、この“キラキラしたデジロック”から“ハードロック”へと変わっていく過程にこそ、私にとってオンリーワンな個性と魅力が詰まっていました。
しかも1990年代前半は、「太陽のKomachi Angel」で初のオリコン1位を獲得したのを皮切りに、「LADY NAVIGATION」「BLOWIN'」「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」「裸足の女神」「MOTEL」など、アルバム未収録のシングルヒットも数多く生まれました。
そういえば、「孤独のRunaway」が収録されている『MARS』も1991年5月にリリースされていますよね。これも忘れちゃいけません。
そんな中で特に記憶に残っているのが、1991年の『IN THE LIFE』、1992年の『RUN』、そして同じく1992年にリリースされたミニアルバム『FRIENDS』。
わずか1年あまりの間に、これほど完成度の高い3作が続けて生まれたという事実は、本当にすごいことだと思うんですよね。
【B'z / 恋じゃなくなる日【B'z presents LIVE FRIENDS】[SOUND ONLY]】
やっぱり「Friends」収録のバージョンが最高なんですけど、歳月を重ねて歌ったこのバージョン↑も味がありますね…。
②RUNのCDリリース前、B'zがラジオ…
そうそう、当時「RUN」のCDリリース前、プロモーションを兼ねてだと思うんですけど、B'zが一日だけラジオ番組をやっていたんですよ。
そこで先行オンエアされた「RUN」の収録曲をカセットテープに録音しては、発売日まで繰り返し聴いていたっけ…。
たしか稲葉さんが「利きカップラーメン」に挑戦していたような…。でも、あの徹底した体調管理で有名な稲葉さんが、プライベートでカップラーメンを食べるとも思えないし…ちょっと記憶があいまいです(笑)。
とまあ、中学生の頃の私はとにかくB'zばかり聴いていました。
中でも衝撃を受けたのが『FRIENDS』です。このアルバムは、ただのミニアルバムという枠を超えて、まるで短編映画や小説を読むような感覚の作品。
特に「恋じゃなくなる日」がすごい。ファンの間では、この曲こそが『FRIENDS』の真のハイライトだと感じている人も多いんじゃないかな。
もちろん「いつかのメリークリスマス」は、毎年クリスマスになるとメディアでも取り上げられるほどの代表曲です。
でも、B'zファンにとっては、インパクトが強かったのは「恋じゃなくなる日」だった、という人も少なくないはず。
③歌詞に全然 "繰り返し" が…
まず何より驚いたのは、歌詞に全然 “繰り返し” が無いこと。
当時のビーイング系(ZARD・WANDS・T-BOLAN・DEENなど)は、キャッチーなサビの繰り返しが“売れるJ-POPの王道”だった時代。そんな中、B'zはあえてそのセオリーを外して、繰り返しのないストーリー重視の詞と構成で挑戦してきた。
まるでひとつの詩を読み進めていくような、あるいは短い映画を観ているような曲の流れ。サビですら一度きりだからこそ、心に強く残るのかもしれません。
そして、あのイントロ。
前曲「Love is...」がしっとりと静かに終わり、余韻が残るなかで、突然鋭いギターとシンセサイザーが絡むように入ってくる。この展開がたまらないんですよね。
ファーストコンタクトで「Love is...」から続けて聴くのとそうじゃないのとでは、印象はだいぶ変わってくるでしょうね…。。
④アルバム全体を通して聴いたときにだけ…
『FRIENDS』は、どの曲もひとつひとつ独立したテーマを持っているのに、アルバム全体を通して聴いたときにだけ、登場人物たちの背景や心の動き、選択がじわじわと浮かび上がってくるように作られています。
たとえば——
冬の海辺をあてもなく歩いて 二人で貝殻集めて
人もまばらな橋の上のベンチで いつまでも波音を聞いている
この描写には、冬ならではの静けさと寂しさがじんわりと染みてきます。
澄み切った冷たい空気、響く波音、人の気配がない景色…。
その風景に、乾いたギターの音が重なることで、心の中の温度まで感じ取れるような気がするんです。
冷たい風が僕らを近づける
くすぶる想い見透かすように
強い戸惑いを意味のない笑顔に
すりかえてまた戸惑う
ここは、男の迷いや戸惑いがギュッと詰まった部分。
本音を言えないまま、笑顔で取り繕ってしまう。
でも本当は、全然平気じゃないし、どうしたらいいかもわからない。
その場をごまかしてしまったことで、さらに戸惑いが深まってしまう。
小さな貝殻にひとつずつ絵を描いて
おもいでを砂に埋めてゆく
それまで写実的だった歌詞が、ここだけ抽象的な表現になる。
これは、お互いの気持ちに踏み込まずに、思い出をそっと整理していくような描写。
言葉にできなかったことを、自分なりに受け止めようとしているように見えます。
真夜中 舗道で突然その腕を
組んできた君はとても綺麗で
ここで初めて「君」が行動します。
それまで「僕」の視点だけで淡々と綴られていた物語のなかで、突然ふたりの距離が縮まる場面。
それだけで、「君」も実は同じ気持ちを抱えていたことが伝わってくる。
きっと、言葉にしなくてもわかってしまう瞬間って、こういうことなんだと思います。
『FRIENDS』は、8曲で1曲。
曲と曲の境界さえも、感情の流れでつながっていて、それぞれの曲が次の曲へと想いをつないでいきます。
一曲ごとに切り取って聴くこともできるけど、通して聴いてこそ見えてくるものがある。
だからこそ、こう思うんです。
もし「恋じゃなくなる日」がなかったら、『FRIENDS』はここまで多くの人に語られる作品にはならなかったんじゃないか。
それくらい、この曲の存在は大きいと思います。
『FRIENDS(友だち)』という言葉は、一見やさしい響きを持っているけれど、このアルバムに出てくる「友達」は、ただの仲の良い関係ではない。
一度は恋人になったふたりが、関係を見つめ直した末にたどり着いた場所。
離れたくないけど、うまくはいかない。
気持ちが残っているからこそ、すっぱりとは終われない。
そんな落としどころのない“距離感”が、このアルバムにはずっと流れているような気がします。